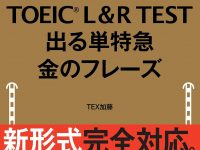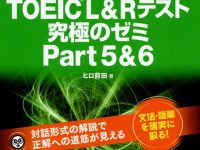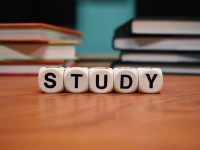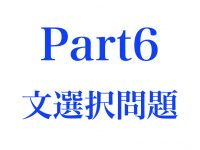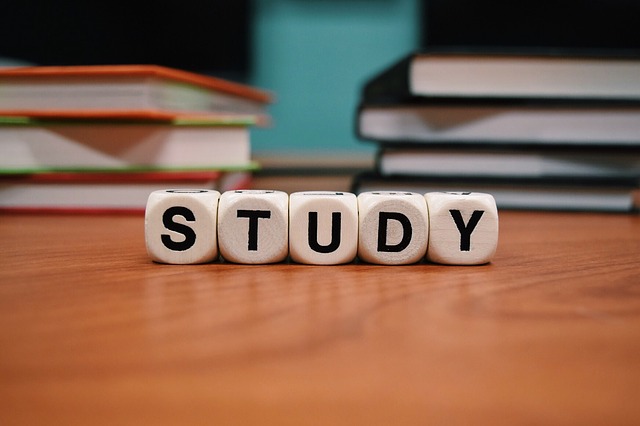
Wokandapix / Pixabay
TOEICで600点以上を取りたいという人向けに個人的にやっておいたほうが良いと思う参考書や問題集をここでは紹介していきたいと思います。
600点をなかな超えられずに悩んでいるという人の参考になれば幸いです!
目次
600点以下の人の特徴
参考書を紹介していく前にTOEICで600点を超えられない人の特徴について書いていきたいと思います。
自己分析をせずに闇雲に勉強をするよりも、600点以上を取るためにはどんな能力が必要で、自分には何が足りていないのかをきちんと理解してから勉強したほうが成績は伸びます。
まずは、自分が今どういった位置にいるのか知ることから始めましょう。
高校レベルの文法で怪しいところがある
TOEICで高得点を取るためには高校レベルの文法知識がどうしても必要となってきます。
400〜500点レベルの人だと高校レベルの文法をきちんと理解できていない可能性があります。
他動詞と自動詞の違い、形容詞や副詞の使い分け、不定詞、動名詞、分詞、関係詞などの使い方がいまいち理解できていない、自信がないという方は文法の復習から始めたほうがいいでしょう。
TOEICの問題集などはこれらの文法を理解していることを前提に話が始まることが多いため、理解していない人にとってはかなりとっつきにくく、難解です。そのため参考書・問題集の解説がよくわからないという状態に陥ってしまいます。その状態で問題集をやっても、ただ問題を解くだけで理解ができていないという最悪な結果になるので、それを避けるためにもまずは文法の復習から始めましょう。
※おすすめの参考書などは後述
TOEIC頻出語彙を知らない
TOEIC600点以下の人の特徴として、TOEICによく出る単語をほとんど知らないということが挙げられます。
大学受験で相当単語を覚えたという人でも、TOEICの単語勉強をしていないと600点を取れるか取れないかレベルです。
私も大学受験時代に相当単語を覚えた自信がありましたが、初めてTOEICを受けた時は知らない単語にかなり遭遇し、Part7の文書の半分以上をほぼ理解できませんでした。さらに文章を読むのに時間がかかりすぎて20問以上塗り絵をしてしまいました。
英文に含まれる単語の内、9割以上の単語を理解していないと、その英文は理解できないと言われています。
大学受験の単語レベルでTOEICの文章の9割の単語を網羅することはできません。Part7に出てくる文書のストーリーがきちんと理解できずに「なんとなくこんな感じの話だろう」で読み進めてしまっている人は語彙力が足りていません。
語彙力を増やすだけで、文書のストーリーが理解できるようになり、読解スピードも上がります。
語彙がスコアに及ぼす影響が最も大きいと個人的には考えています。600点以下の人の最優先事項は(TOEICの)語彙力を増やすことです。
解き方・テクニックを知らない
TOEICではパートごとの解き方やテクニックを知っているのと知らないのとでは大きく差がでます。
解き方やテクニックを知っていると、正解への道筋が見えやすくなったり、解答時間の短縮もできます。
昔と比べるとテクニックだけで解ける問題は減りましたが、それでもテクニックは有効です。
高得点が取れないという人は解き方やテクニックを知らずにただ闇雲に問題を解いているという人が多いのではないでしょうか。
私自身も初めてTOEICを受けた時は解き方もなにも知らずにただひたすら問題を解いていました。後に参考書を買いそこでパートごとの解き方を知ってからは問題がかなり解きやすくなったと実感しました。
文法と語彙を押さえたら、次はパートごとの解き方・テクニックを学ぶのがおすすめです。
※解き方・テクニックが学べる参考書は後述
45分間英語を聴くことに慣れていない
TOEICのリスニングは45分間で、1分たりとも気を抜くことはできません。途中で気を抜こうものなら、音声についていけなくなり、正解することはできません。
特に厳しくなるのはPart3,4です。ここから聞き取らなければいけない情報が一気に増えます。リスニング力だけでなく、情報処理能力と集中力も問われるパートでもあります。
Part3と4は音声が流れる前に設問を先読みしておくのが基本的な解き方です。問題を解いたらすぐに次の設問の先読みを始めます。そのため休んでいる暇はありません。(先読みについてはこちらを参照「TOEIC Part3・4で設問を先読みすることの重要性とコツ」)
この「先読みをしながら問題を解く」を最後までやり続ける集中力と体力をつけることが大事です。
600点を超えられないという人は、45分間英語聞き、問題を解くということに慣れておくのも大事です。
リーディングセクションの時間配分ができていない
TOEICのリーディングセクションは時間との勝負です。800点台の人でも時間内に最後まで解き終わらないことが多いです。600点以下の人の多くはPart7の後半のほとんどが塗り絵になってしまっているのではないでしょうか。
最後まで解き終わらない原因としてはPart5&6に時間をかけすぎてしまっている、Part7の読解スピード、解答スピードが遅いということが挙げられます。
リーディングセクションの時間配分としてはPat5とPart6を20分以内に終え、Part7に55分以上当てるのが理想です。ただ、Part5,6を急いで解いて間違えてしまったら意味が無いので、正確に速く解く練習をしなければなりません。
600点以上が目標であれば、まずはPart5,6の問題をとにかくたくさん解き、解答スピードと正確さを上げることが重要です。
そして日頃から時間を意識して問題を解くようにしましょう。Part5であれば、1問あたり20秒以内を目安に解く練習をし、Part6であれば1文書あたり2分〜2分半以内で解く練習をしておくといいです。
※時間配分に関してはこちらを参照「TOEIC新形式リーディングセクションの時間配分について【Part5,6,7】」
解いた問題の数が少ない
TOEICには頻出の問題があり、またTOEIC特有のストーリー展開というものがあります。例えばリスニングセクションであれば、飛行機の遅延の話であったり、出張の話、会社の面接の話など出題されるテーマがある程度決まっています。そのためTOEICを何回も受けている人はなんとなくストーリーの展開が予測できてしまいます。これはリーディングのPart7でも同じことが言えます。
また、TOEICは基本的にビジネス関連の話がよく出ます。そのため、社会経験のない学生ははっきり言って不利です。商品の受注発注の話や製品のプレゼン、会社のセミナーの話など学生のうちにあまり関わることがない話が出てくるとうまく理解できません(英語のため余計に)。
事前にTOEICの問題をたくさん解いておけば、頻出のストーリーやビジネス関連のテーマに強くなれます。いきなり、商品の受注発注の話を読んでもいまいち理解できませんが、前に同じような話の問題を解いていれば理解しやすく読みやすいです。
TOEICの問題集を使ってできるだけたくさんのテーマ、ストーリー、設問パターンに慣れておくことも高得点を取るための鍵となります。
やっておくべき参考書・問題集
ここからは個人的におすすめできる参考書や問題集を紹介して行きたいと思います。どれもやっておいて損はないはずです!
文法関連
中学レベルの文法が怪しいし、難しい用語がたくさん出てくると理解できないという人には「中学 英語を もう一度ひとつひとつわかりやすく。」をおすすめします。
かなり丁寧な解説がなされているので、英語に苦手意識がある人でも読みやすく理解もしやすいです。まずはこの1冊で中学英語をしっかりと押さえましょう。
高校レベルの文法に自信がないという方におすすめなのが「一億人の英文法」です。
従来の文法書だと「なぜそうなるの?」という疑問が残ることが多々ありましたが、この本では「なぜそうなるのか」を詳しく解説しています。またネイティブスピーカー視点での解説もなされているのが大きな特徴の1つです。
網羅性も高く、この1冊をやっておけば英文法で困ることはないでしょう。
TOEIC単語帳
TOEICの単語帳に関しては「TOEIC L & R TEST 出る単特急 金のフレーズ」を1冊完璧にやりこめば確実に600点以上は取ることができます。
金のフレーズは得点別に単語が分かれています。600点レベル、730点レベル、860点レベル、990点レベルの4段階となっています。
600点以上が目標であれば730点レベルまでの単語は完璧に、860点レベルの単語も押さえておきたいところです。990点レベルに関しては800点以上を目指すのであればやっておくべきですが、600点以上が目標であれば無理をしてやる必要はありません。
860点レベルまで終わらせたら最初に戻り2周目をやるのがおすすめです。
TOEIC参考書
上で述べたように解き方やテクニックを知ることがTOEICでは非常に重要です。
そこでパートごとの解き方やテクニックを解説してくれている参考書をここでは紹介します。苦手なパートや時間がかかりすぎてしまうパートがあれば買うことをおすすめします。
Part1,2
全パートを通しておすすめなのが「究極のゼミ」シリーズです。TOEICを毎回受け、分析をしているヒロ前田という方が作成している参考書・問題集です。
これはPart1と2を扱っていますが、配分的にはPart2が8割、Part1は2割程度の配分です。
Part2が苦手という人に特におすすめです。
この本ではPart2に出てくる質問文を①Yes/No疑問文、②WH疑問文、③提案・命令・依頼、④メッセージ、⑤パニック型に分類し、それぞれの特徴・解き方・テクニック・コツなどを解説しています。
また応答文に関しても、直接的な応答と間接的な応答の2つについて詳しく解説がなされているので、この1冊でほぼPart2の解き方はマスターできます。
また、最後にはミニ模試もついているため、実際に学んだことを活かして、問題を解く練習もできます。
Part3,4
こちらはPart3と4を扱った究極のゼミです。
Part3,4それぞれの設問をパターン分けして、解説しています。
Part3と4は問題数も多く、難易度も高いため、こういった解き方を学べる本を1冊やっておくことをおすすめします。
Part5,6
解説がかなり丁寧な方が良いという方は「究極のゼミ Part5&6」を、解説少々・問題多めが良いという方は「文法特急」「単語特急」がおすすめです。
Part5,6をどれだけ正確に早く解けるかがTOEICでは鍵となります。解き方やテクニックを知ったあとはできるだけたくさんの問題を解くようにしましょう。文法特急と単語特急には続編も出ているので、余裕があればそちらもやることをおすすめします。
Part7
Part7でも「究極のゼミ Part7」がおすすめです。私はこの1冊をやっただけでかなりPart7が解きやすくなりました。究極のゼミをやる前はダブルパッセージには手も足も出ないという状態でしたが、やった後は解き方がわかり、間違えることも少なくなりました。
Part7を解くのに時間がかかる、上手く読み進められない、自信を持って答えを選ぶことができない、こういったことに心当たりがある人は是非「究極のゼミ Part7」をやることをおすすめします。
公式問題集
TOEICテストはETSというところが作成しているのですが、そのETSが作っているTOEICの問題集があります。それが「TOEIC公式問題集」です。
同じところが作っているだけあり、問題の質は本番のテストとほぼ変わりません。TOEICを受けたことがないという人は事前に絶対にやっておきましょう。公式問題集についてはこちらに詳しく書いたので参考にして下さい「TOEICのリスニング対策で公式問題集を絶対にやっておくべき理由」
ただ、いきなり公式問題集をやるよりは、まず上記の参考者や問題集をやりパートごとの基本的な解き方・テクニックを知ってから、公式問題集をやるのがおすすめです。公式問題集はいわば最後の仕上げのようなものです。
公式問題集はこれまでに何冊か出ていますが、基本的には新しいのがおすすめです。今なら新形式に対応している以下の4冊がおすすめです。
800点、900点を狙うのであれば3冊全てをやっておきたいところですが、600点以上が目標という方はとりあえずこの中の1冊を完璧にしておきましょう。
『公式 TOEIC Listening & Reading 問題集 3』は2017年12月8日に発売された一番新しい公式問題集となっております。今のTOEICの傾向を一番反映している公式問題集と言っても過言ではないので、どれを買おうか悩んでいる方はこちらを買っておけば間違いありません。